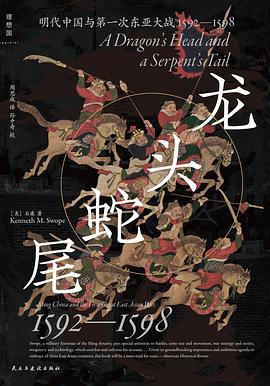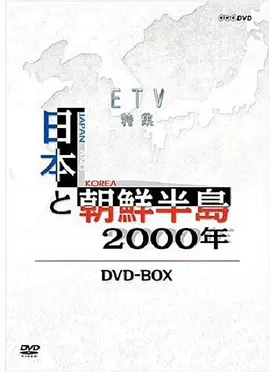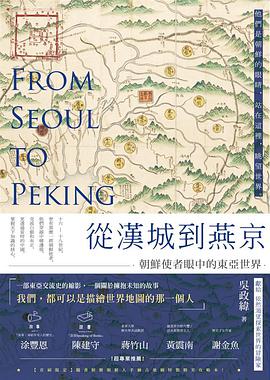龙头蛇尾 豆瓣
A Dragon’s Head and a Serpent’s Tail: Ming China and the First Great East Asian War, 1592—1598
6.9 (7 个评分)
作者:
[美]石康(Kenneth M.Swope)
译者:
周思成
民主与建设出版社
2023
全景描绘万历皇帝与丰臣秀吉的史诗对决
生动还原扣人心弦的战斗场面
展现明、朝、日三国政治经济、军事技术、外交的全面竞争
揭示东亚朝贡体系的实际运作
---------------------------------------
◎内容简介
16世纪末,经过张居正的改革,明朝一扫颓势,年轻的万历皇帝采取积极和颇见成效的边疆政策,延续了明朝的军事中兴,但朝廷党争也愈演愈烈。未来的后金汗努尔哈赤征服女真各部,成为一支不容忽视的新兴力量。宣祖李昖治下的朝鲜饱受党争之扰,内政荒疏,军备废弛。出身卑微的战国枭雄丰臣秀吉平定各方势力,渐次统一日本列岛,开始把目光投向大陆。
1592年春,企图征服明朝的丰臣秀吉集结大军于名护屋城,下达了渡海侵略作战的命令,兵锋直指朝鲜。5月,日军登陆釜山,一路势如破竹,朝鲜君臣无力招架,紧急向明廷求援,一场持续六年、投入数十万将士的东亚大战由此拉开序幕。
在本书中,军事史家石康重视运用中方史料,关注战争动员、战略战术、军事技术、后勤补给和战场环境,分析内政、外交与军事的互动,对围城战、山地野战和海战等诸多战斗细节的描述扣人心弦,立体地讲述了这场大战的来龙去脉。在他看来,万历援朝之役是近代东亚历史上具有决定性意义的一场战争,不仅改变了当时三国的历史走向,也深深影响了今天的东亚地缘政治格局。
---------------------------------------
◎编辑推荐
★从明朝视角来研究万历援朝之役,详述来龙去脉
作者回顾了明朝出兵援朝的历史背景、16世纪三国之间的冲突,描写了持续六年的东亚大战的全过程,诸如军力配备、日军攻势、朝鲜官军的一触即溃、地方武装和僧兵的战斗、明军出兵过程、朝鲜的军事改革、战后处置等。
★《隳三都》作者周思成老师翻译,精彩再现惊心动魄的战斗细节
书中着意描绘了一系列围城战、山地野战和海战,如忠州之战、玉浦海战、闲山岛海战、平壤大捷、碧蹄馆之战、晋州城攻防战、南原之战、稷山之战、鸣梁海战、蔚山倭城攻防战、露梁海战等。
★比较三国的军事技术、动员能力、后勤补给和内政外交的优劣
分析三国军事技术长短,特别关注武器与战术、武将性格与能力。既展现了三国各自的体系如何应对战争,也没有忽视朝廷的党争,围绕册封丰臣秀吉的争议。外交场合的尔虞我诈也贯穿整场战争。
★刻画了虽有种种缺陷,却竭力维护明朝军事霸权的万历帝形象
在叙述战争事件的过程中,作者凸显了万历帝在明代国家中的关键角色。
★透过战争看朝贡体系的实际运作与明末清初的东亚局势
朝鲜求援、议和过程中的误解和龃龉、导致战火重燃的恐吓、封贡之争都是朝贡体系的体现。大战之后,明朝和日本的历史走向发生了剧烈变化。
---------------------------------------
◎评价与推荐
本书是西方少有的从明朝角度来研究万历朝鲜之役的著作。在东西方战争史比较研究视野下,作者既考察了日、韩史料,也充分利用了明、清史料;既参考了西方与日、韩研究论著,也关注到当代中国的学术观点,因而本书史料充分,观点鲜明,持论相对客观。本书强调万历时期的明朝依然有强大的军事能力与高效的官僚体系,用充分的史实,展示了明军在战争中的主导地位,一定程度上纠正了日、韩学者的偏见。本书对于作战双方的战略战术、武器装备、后勤供给等方面都有精彩论述,深化了这场战争的系统认识,值得推介。
——孙卫国(南开大学历史学院教授)
壬辰战争,即石康所谓的“第一次东亚大战”,是影响16世纪末以来东亚历史走向的关键事件,其余波影响至今。《龙头蛇尾》一书综合使用明朝、朝鲜、日本三方的史料,并参考基督教士留下的记录,细致描绘了这场战争的来龙去脉与历史回响,尤其深入刻画了虽有种种缺陷,却竭力维护明朝军事霸权的万历帝形象,是一部发人深省的历史著作。
——丁晨楠(山东大学历史文化学院副研究员)
生动还原扣人心弦的战斗场面
展现明、朝、日三国政治经济、军事技术、外交的全面竞争
揭示东亚朝贡体系的实际运作
---------------------------------------
◎内容简介
16世纪末,经过张居正的改革,明朝一扫颓势,年轻的万历皇帝采取积极和颇见成效的边疆政策,延续了明朝的军事中兴,但朝廷党争也愈演愈烈。未来的后金汗努尔哈赤征服女真各部,成为一支不容忽视的新兴力量。宣祖李昖治下的朝鲜饱受党争之扰,内政荒疏,军备废弛。出身卑微的战国枭雄丰臣秀吉平定各方势力,渐次统一日本列岛,开始把目光投向大陆。
1592年春,企图征服明朝的丰臣秀吉集结大军于名护屋城,下达了渡海侵略作战的命令,兵锋直指朝鲜。5月,日军登陆釜山,一路势如破竹,朝鲜君臣无力招架,紧急向明廷求援,一场持续六年、投入数十万将士的东亚大战由此拉开序幕。
在本书中,军事史家石康重视运用中方史料,关注战争动员、战略战术、军事技术、后勤补给和战场环境,分析内政、外交与军事的互动,对围城战、山地野战和海战等诸多战斗细节的描述扣人心弦,立体地讲述了这场大战的来龙去脉。在他看来,万历援朝之役是近代东亚历史上具有决定性意义的一场战争,不仅改变了当时三国的历史走向,也深深影响了今天的东亚地缘政治格局。
---------------------------------------
◎编辑推荐
★从明朝视角来研究万历援朝之役,详述来龙去脉
作者回顾了明朝出兵援朝的历史背景、16世纪三国之间的冲突,描写了持续六年的东亚大战的全过程,诸如军力配备、日军攻势、朝鲜官军的一触即溃、地方武装和僧兵的战斗、明军出兵过程、朝鲜的军事改革、战后处置等。
★《隳三都》作者周思成老师翻译,精彩再现惊心动魄的战斗细节
书中着意描绘了一系列围城战、山地野战和海战,如忠州之战、玉浦海战、闲山岛海战、平壤大捷、碧蹄馆之战、晋州城攻防战、南原之战、稷山之战、鸣梁海战、蔚山倭城攻防战、露梁海战等。
★比较三国的军事技术、动员能力、后勤补给和内政外交的优劣
分析三国军事技术长短,特别关注武器与战术、武将性格与能力。既展现了三国各自的体系如何应对战争,也没有忽视朝廷的党争,围绕册封丰臣秀吉的争议。外交场合的尔虞我诈也贯穿整场战争。
★刻画了虽有种种缺陷,却竭力维护明朝军事霸权的万历帝形象
在叙述战争事件的过程中,作者凸显了万历帝在明代国家中的关键角色。
★透过战争看朝贡体系的实际运作与明末清初的东亚局势
朝鲜求援、议和过程中的误解和龃龉、导致战火重燃的恐吓、封贡之争都是朝贡体系的体现。大战之后,明朝和日本的历史走向发生了剧烈变化。
---------------------------------------
◎评价与推荐
本书是西方少有的从明朝角度来研究万历朝鲜之役的著作。在东西方战争史比较研究视野下,作者既考察了日、韩史料,也充分利用了明、清史料;既参考了西方与日、韩研究论著,也关注到当代中国的学术观点,因而本书史料充分,观点鲜明,持论相对客观。本书强调万历时期的明朝依然有强大的军事能力与高效的官僚体系,用充分的史实,展示了明军在战争中的主导地位,一定程度上纠正了日、韩学者的偏见。本书对于作战双方的战略战术、武器装备、后勤供给等方面都有精彩论述,深化了这场战争的系统认识,值得推介。
——孙卫国(南开大学历史学院教授)
壬辰战争,即石康所谓的“第一次东亚大战”,是影响16世纪末以来东亚历史走向的关键事件,其余波影响至今。《龙头蛇尾》一书综合使用明朝、朝鲜、日本三方的史料,并参考基督教士留下的记录,细致描绘了这场战争的来龙去脉与历史回响,尤其深入刻画了虽有种种缺陷,却竭力维护明朝军事霸权的万历帝形象,是一部发人深省的历史著作。
——丁晨楠(山东大学历史文化学院副研究员)